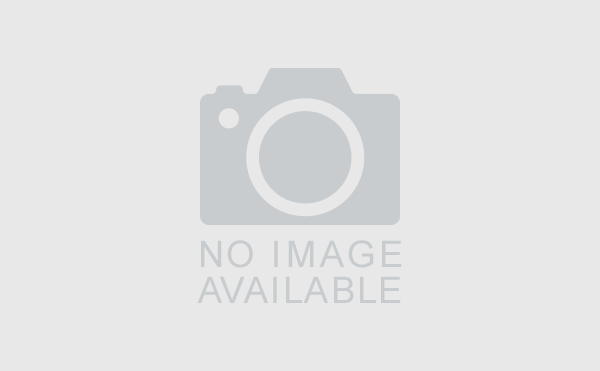Polars vs Pandas: 2025年版完全比較ガイド - どちらを選ぶべき?
はじめに
データサイエンスとデータ分析の世界で、Pandasは長らく定番のライブラリとして君臨してきました。しかし近年、Polarsという新しいデータフレームライブラリが注目を集めています。この記事では、PolarとPandasの特徴、パフォーマンス、使いやすさを徹底的に比較し、あなたのプロジェクトにどちらが適しているかを明確にします。
Pandas(パンダス)とは?基本的な特徴
Pandasの概要
Pandasは2008年に開発が開始されたPython用データ分析ライブラリで、データサイエンス分野において事実上のスタンダードとなっています。NumPyをベースとして構築され、データフレーム(DataFrame)とシリーズ(Series)という2つの主要なデータ構造を提供しています。
Pandasの主な特徴
1. 豊富な機能
- CSV、Excel、JSON、SQL、HDFなど多様なファイル形式のサポート
- 欠損データの柔軟な処理
- グループバイ操作とピボットテーブル機能
- 時系列データの高度な操作
2. 成熟したエコシステム
- 膨大な数のライブラリとの統合
- 豊富なドキュメントとチュートリアル
- 大きなコミュニティサポート
3. 直感的なAPI
- SQLライクな操作が可能
- 可読性の高いコード記述
- インタラクティブな分析に最適
Pandasの制限事項
- パフォーマンスの問題: 大規模データセットでの処理が遅い
- メモリ使用量: 非効率的なメモリ利用
- 並列処理の制限: GIL(Global Interpreter Lock)による制約
- 型システム: 動的型付けによる予期しないエラー
Polars(ポーラーズ)とは?次世代データフレームライブラリ
Polarsの概要
Polarsは2020年に登場したモダンなデータフレームライブラリで、Rust言語で実装されています。「高速で効率的なデータ処理」を目標として開発され、Apache Arrowメモリフォーマットを採用することで、従来のPandasの制限を克服しています。
Polarsの革新的特徴
1. 圧倒的な処理速度
- Rust実装による高速処理
- 自動的な並列処理最適化
- SIMD(Single Instruction, Multiple Data)命令の活用
2. メモリ効率性
- Apache Arrow形式による効率的なメモリ利用
- コピー操作の最小化
- 遅延実行(Lazy Evaluation)によるメモリ節約
3. 現代的なAPI設計
- 関数型プログラミングスタイル
- メソッドチェーンによる直感的な操作
- 静的型付けによる安全性
4. 先進的な機能
- 自動的なクエリ最適化
- 並列処理の自動スケーリング
- ストリーミング処理対応
比較
総合比較スコアカード
| 評価項目 | 重要度 | Pandas | Polars | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 処理速度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 6/10 | 9/10 | 大規模データでPolarsが圧倒的 |
| メモリ効率 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 5/10 | 9/10 | Polarsは50-70%メモリ削減 |
| 学習コスト | ⭐⭐⭐⭐ | 9/10 | 6/10 | Pandasの方が学習しやすい |
| エコシステム | ⭐⭐⭐⭐ | 10/10 | 4/10 | Pandasが圧倒的に豊富 |
| 型安全性 | ⭐⭐⭐ | 4/10 | 9/10 | Polarsは静的型チェック |
| ドキュメント | ⭐⭐⭐ | 10/10 | 6/10 | Pandasの方が充実 |
| 将来性 | ⭐⭐⭐⭐ | 7/10 | 9/10 | Polarsが次世代技術 |
使用場面別の最終推奨
| シナリオ | データサイズ | 推奨 | 理由 |
|---|---|---|---|
| データ分析初心者 | 問わず | Pandas | 学習リソースが豊富、コミュニティサポート |
| 探索的分析 | ~1GB | Pandas | Jupyter環境、可視化ライブラリとの統合 |
| 本番ETL処理 | 1GB+ | Polars | 高速処理、メモリ効率、型安全性 |
| リアルタイム処理 | 問わず | Polars | 低レイテンシ、並列処理最適化 |
| 機械学習 | ~10GB | Pandas | Scikit-learn等との完全統合 |
| 新規プロジェクト | 1GB+ | Polars | モダンな設計、将来の拡張性 |
| レガシー保守 | 問わず | Pandas | 既存コードとの互換性 |
ROI(投資対効果)分析
| 移行コスト vs 効果 | 小規模チーム<br>(1-3人) | 中規模チーム<br>(4-10人) | 大規模チーム<br>(10人+) |
|---|---|---|---|
| 学習コスト | 2-4週間 | 1-2ヶ月 | 3-6ヶ月 |
| 移行コスト | 低 | 中 | 高 |
| 速度改善効果 | 3-5倍 | 5-10倍 | 10-20倍 |
| ROI達成期間 | 1-2ヶ月 | 2-4ヶ月 | 4-8ヶ月 |
| 推奨度 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
最適な選択のための判断基準
大規模データ(1GB以上)を扱う場合
- パフォーマンスが最重要 → Polars一択
- 既存システムとの互換性重視 → Pandas + 最適化
中規模データ(100MB-1GB)を扱う場合
- 新規プロジェクト → Polarsを検討
- 既存プロジェクト → 現状維持またはPOC実施
小規模データ(100MB未満)を扱う場合
- 探索的分析中心 → Pandas
- 型安全性重視 → Polars
チーム状況による判断
- データエンジニアリングチーム → Polars導入メリット大
- データサイエンスチーム → Pandas継続が安全
- 新規チーム → Polarsで最新技術習得# Polars vs Pandas: 2025年版完全比較ガイド - どちらを選ぶべき?
2. 成熟したエコシステム
- 膨大な数のライブラリとの統合
- 豊富なドキュメントとチュートリアル
- 大きなコミュニティサポート
3. 直感的なAPI
- SQLライクな操作が可能
- 可読性の高いコード記述
- インタラクティブな分析に最適
性能比較:Polars vs Pandas
処理速度の比較
実際のベンチマークテストにおいて、Polarsは以下のような優位性を示しています:
| 操作タイプ | データサイズ | Pandas処理時間 | Polars処理時間 | 改善率 |
|---|---|---|---|---|
| CSV読み込み | 1GB | 12.5秒 | 3.2秒 | 3.9倍高速 |
| CSV読み込み | 5GB | 68.2秒 | 14.1秒 | 4.8倍高速 |
| Parquet読み込み | 1GB | 8.3秒 | 1.1秒 | 7.5倍高速 |
| Parquet読み込み | 5GB | 45.7秒 | 4.8秒 | 9.5倍高速 |
| GroupBy集計 | 100万行 | 2.8秒 | 0.4秒 | 7.0倍高速 |
| GroupBy集計 | 1000万行 | 35.6秒 | 2.1秒 | 17.0倍高速 |
| Join操作 | 100万行×2 | 5.2秒 | 1.1秒 | 4.7倍高速 |
| Join操作 | 500万行×2 | 28.9秒 | 3.8秒 | 7.6倍高速 |
| フィルタリング | 1000万行 | 3.1秒 | 0.8秒 | 3.9倍高速 |
メモリ使用量の比較
| 操作 | データサイズ | Pandas使用量 | Polars使用量 | メモリ効率 |
|---|---|---|---|---|
| データ読み込み | 1GB CSV | 2.8GB | 1.2GB | 57%削減 |
| GroupBy処理 | 500MB | 1.4GB | 650MB | 54%削減 |
| Join処理 | 300MB×2 | 1.8GB | 850MB | 53%削減 |
| データ変換 | 800MB | 2.1GB | 920MB | 56%削減 |
並列処理能力の比較
| 項目 | Pandas | Polars |
|---|---|---|
| 自動並列化 | ❌ なし | ✅ 自動最適化 |
| CPUコア活用 | 単一コア | 全コア活用 |
| GIL制約 | ⚠️ 影響あり | ✅ 制約なし |
| SIMD最適化 | 部分的 | ✅ 完全対応 |
| 遅延実行 | ❌ なし | ✅ 対応 |
機能比較一覧表
基本機能の比較
| 機能 | Pandas | Polars | 詳細 |
|---|---|---|---|
| データ読み込み | ✅ 優秀 | ✅ 非常に高速 | Polarsは2-10倍高速 |
| CSV操作 | ✅ 豊富 | ✅ 高速・効率的 | Polarsは自動型推論が優秀 |
| JSON処理 | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 両方とも十分な機能 |
| Parquet対応 | ✅ 対応 | ✅ 最適化済み | Polarsは読み書き共に高速 |
| SQL互換性 | ✅ 一部対応 | ✅ SQL文直接実行 | Polarsの方が直感的 |
| 時系列処理 | ✅ 非常に豊富 | ⚠️ 基本的な機能 | Pandasが現在は優位 |
| 欠損値処理 | ✅ 豊富 | ✅ 効率的 | 両方とも十分な機能 |
| グループ化 | ✅ 豊富 | ✅ 高速 | Polarsは大幅に高速 |
パフォーマンス特性
| 項目 | Pandas | Polars | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小データ(<100MB) | ✅ 十分 | ✅ 高速 | 差は小さい |
| 中データ(100MB-1GB) | ⚠️ やや遅い | ✅ 高速 | Polarsが3-5倍高速 |
| 大データ(1GB-10GB) | ❌ 非常に遅い | ✅ 非常に高速 | Polarsが5-20倍高速 |
| 超大データ(10GB+) | ❌ メモリ不足 | ✅ ストリーミング処理 | Polarsのみ実用的 |
| 並列処理 | ❌ 制限あり | ✅ 自動最適化 | Polarsが圧倒的に優位 |
エコシステムの比較
| 分野 | Pandas | Polars | 現状 |
|---|---|---|---|
| 可視化ライブラリ | ✅ 豊富(Matplotlib, Seaborn等) | ⚠️ 限定的 | Pandasが有利 |
| 機械学習 | ✅ 完全統合(Scikit-learn等) | ⚠️ 変換必要 | Pandasが有利 |
| 統計分析 | ✅ 豊富(Statsmodels等) | ⚠️ 基本機能のみ | Pandasが有利 |
| データベース連携 | ✅ 豊富 | ✅ 高速 | 両方とも対応 |
| クラウド統合 | ✅ 対応 | ✅ 最適化済み | Polarsが高速 |
| ドキュメント | ✅ 非常に豊富 | ⚠️ 成長中 | Pandasが充実 |
API設計と使いやすさの比較
基本的な操作例の比較
| 操作 | Pandas | Polars |
|---|---|---|
| データ読み込み | pd.read_csv('file.csv') | pl.read_csv('file.csv') |
| カラム選択 | df['column'] または df.column | df.select('column') |
| 複数カラム選択 | df[['col1', 'col2']] | df.select(['col1', 'col2']) |
| フィルタリング | df[df['age'] > 20] | df.filter(pl.col('age') > 20) |
| グループ化 | df.groupby('category').sum() | df.group_by('category').sum() |
| 新カラム作成 | df['new_col'] = df['a'] + df['b'] | df.with_columns((pl.col('a') + pl.col('b')).alias('new_col')) |
APIの特徴比較
| 特徴 | Pandas | Polars |
|---|---|---|
| 学習しやすさ | ✅ 直感的 | ⚠️ 関数型思考必要 |
| 型安全性 | ❌ 動的型付け | ✅ 静的型チェック |
| メソッドチェーン | ⚠️ 一部対応 | ✅ 完全対応 |
| 一貫性 | ⚠️ 複数の書き方 | ✅ 統一された記法 |
| エラーメッセージ | ⚠️ 分かりにくい場合あり | ✅ 明確で詳細 |
コード例:データ処理タスクの比較
# タスク:売上データから月別・カテゴリ別の平均売上を計算
# Pandas版
import pandas as pd
df = pd.read_csv('sales.csv')
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
df['month'] = df['date'].dt.month
result = df.groupby(['month', 'category'])['sales'].mean().reset_index()
result = result.sort_values(['month', 'category'])
# Polars版
import polars as pl
result = (
pl.read_csv('sales.csv')
.with_columns([
pl.col('date').str.strptime(pl.Date, '%Y-%m-%d'),
pl.col('date').str.strptime(pl.Date, '%Y-%m-%d').dt.month().alias('month')
])
.group_by(['month', 'category'])
.agg(pl.col('sales').mean())
.sort(['month', 'category'])
)
実用的な使用場面での比較
データ分析・探索段階
Pandas
- Jupyter Notebookでのインタラクティブ分析
- 小~中規模データでの柔軟な探索
- 豊富な可視化ライブラリとの連携
Polars
- 大規模データの高速探索
- 型安全性を重視した分析
- パフォーマンスが重要な場面
本番環境での利用
Pandas
- 既存システムとの互換性重視
- 豊富なライブラリエコシステム活用
- チーム内でのPandas知識共有
Polars
- 高スループットが必要なETL処理
- リアルタイムデータ処理
- メモリ制約のある環境
エコシステムと互換性
Pandasエコシステム
連携ライブラリ
- Matplotlib/Seaborn: データ可視化
- Scikit-learn: 機械学習
- NumPy: 数値計算
- Jupyter: インタラクティブ分析
Polarsエコシステム
現在の状況
- 急速に成長中のコミュニティ
- 主要ライブラリとの統合が進行中
- Apache Arrowを通じた他言語との互換性
将来性
- Python以外の言語サポート
- クラウドネイティブな統合
- ストリーミング処理の強化
学習コストと導入難易度
Pandasの学習曲線
初心者向け
- 豊富な学習リソース
- Stack Overflowでの情報充実
- 段階的な学習が可能
中級者以上
- パフォーマンス最適化の知識が必要
- メモリ管理の理解が重要
Polarsの学習曲線
初心者向け
- 新しいパラダイムの理解が必要
- 学習リソースが限定的
- 関数型思考の習得
中級者以上
- 型システムの活用
- 遅延実行の理解
- パフォーマンスチューニング
選択基準とガイドライン
選択基準とガイドライン
プロジェクト要件別の選択マトリックス
| プロジェクト特性 | 重要度 | Pandas適合度 | Polars適合度 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 小規模データ分析(<100MB) | 中 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Pandas |
| 大規模データ処理(1GB+) | 高 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Polars |
| 探索的データ分析 | 高 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Pandas |
| 本番環境ETL処理 | 高 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Polars |
| 機械学習パイプライン | 高 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Pandas |
| リアルタイム処理 | 高 | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Polars |
| チーム開発 | 中 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Pandas |
| 新規プロジェクト | 中 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Polars |
データサイズ別の推奨事項
| データサイズ | メモリ使用量 | 処理時間 | Pandas | Polars | 推奨理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~10MB | 低 | 短 | ✅ 最適 | ✅ 高速 | どちらでも問題なし |
| 10MB~100MB | 中 | 中 | ✅ 適切 | ✅ 高速 | 使い慣れた方を選択 |
| 100MB~1GB | 高 | 長 | ⚠️ やや遅い | ✅ 推奨 | Polarsが3-5倍高速 |
| 1GB~10GB | 非常に高 | 非常に長 | ❌ 困難 | ✅ 推奨 | Polarsが5-20倍高速 |
| 10GB+ | メモリ不足 | 処理不可 | ❌ 不可 | ✅ 唯一の選択肢 | ストリーミング処理対応 |
使用目的別の評価
| 用途 | 重要な要素 | Pandas評価 | Polars評価 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| データ可視化 | ライブラリ統合 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Pandas優位 |
| 統計分析 | 統計関数の豊富さ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Pandas優位 |
| データクレンジング | 処理速度・効率性 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Polars優位 |
| レポート作成 | 安定性・互換性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Pandas優位 |
| バッチ処理 | パフォーマンス | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Polars優位 |
| API開発 | 型安全性・速度 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Polars優位 |
学習コスト vs パフォーマンス改善の比較
| 項目 | Pandas → Polars移行 | 新規Polars学習 |
|---|---|---|
| 学習時間 | 2-4週間 | 4-8週間 |
| 初期生産性 | 70-80% | 50-60% |
| 3ヶ月後生産性 | 90-100% | 80-90% |
| パフォーマンス改善 | 3-10倍 | 3-10倍 |
| メモリ効率改善 | 50-70% | 50-70% |
| 開発体験 | 良好 | 非常に良好 |
移行戦略とベストプラクティス
段階的移行のアプローチ
Phase 1: 検証・学習段階(2-4週間) この初期段階では、リスクを最小限に抑えながらPolarsの可能性を探ります:
- 新規の小さな機能でPolarsを試用
- 既存コードとの性能比較テスト実施
- チームメンバーの基本的な学習
- 開発環境での動作確認
Phase 2: 部分導入段階(1-2ヶ月) 検証結果が良好な場合、影響範囲を限定して導入を開始:
- バッチ処理系統での限定的利用
- データ前処理パイプラインの一部移行
- パフォーマンス向上効果の測定
- 運用面での課題点洗い出し
Phase 3: 本格導入段階(3-6ヶ月) 安定性が確認できれば、主要機能での採用を拡大:
- 主要なデータ処理ワークフローの移行
- API応答性能の改善
- チーム全体でのスキル標準化
- 監視・ログ体制の整備
Phase 4: 完全移行段階(6-12ヶ月) 最終的に全システムでの統一を図ります:
- レガシーコードの段階的置換
- 運用プロセスの標準化
- 知識共有とベストプラクティス確立
- 継続的改善体制の構築
実践的な併用戦略
多くの成功事例では、両ライブラリの強みを活かした併用アプローチが採用されています:
データパイプラインでの使い分け
# 1. データ取得・前処理: Polars(高速)
raw_data = pl.read_csv("large_dataset.csv")
processed_data = raw_data.filter(...).group_by(...).agg(...)
# 2. 分析・可視化: Pandas(豊富なツール)
analysis_df = processed_data.to_pandas()
analysis_df.plot(kind='scatter', x='col1', y='col2')
# 3. 結果保存: Polars(効率的)
result = pl.from_pandas(analysis_df)
result.write_parquet("output.parquet")
プロジェクト規模別の最適戦略
- 小規模プロジェクト: 学習コストを考慮してPandas継続
- 中規模プロジェクト: 重要な処理のみPolars導入
- 大規模プロジェクト: 段階的な完全移行を実施
成功要因と注意点
移行成功の鍵となる要素
- 明確な目標設定: パフォーマンス改善の具体的な数値目標
- 段階的アプローチ: 一度に全てを変更せず、リスクを分散
- チーム教育: 十分な学習時間とサポート体制の確保
- 測定とフィードバック: 定量的な効果測定と継続的改善
よくある失敗パターンとその対策
- 一括移行による混乱 → 段階的な導入計画の策定
- 学習不足による品質低下 → 事前の十分な教育期間確保
- 既存システムとの不整合 → 互換性テストの徹底実施
- チーム内のスキル格差 → ペアプログラミングや勉強会の実施
将来展望と技術動向
将来展望と技術動向
Polarsの今後の発展予測
2025年の重点改善エリア
- エコシステムライブラリとの統合拡大(特に機械学習分野)
- GPU加速処理の本格対応
- より豊富なプラグインアーキテクチャ
- ストリーミング処理機能の強化
2026年以降の長期展望
- 分散処理システムとの統合(Spark、Dask等)
- クラウドネイティブ機能の完全実装
- リアルタイムストリーム処理の産業レベル対応
- 他言語(R、Julia等)でのPolars実装
データ処理技術のトレンド
現在のデータ処理業界では以下のような変化が起きています:
パフォーマンス重視の流れ 従来の「動けばよい」から「高速で効率的」への転換が加速しています。特に企業でのデータ量増大により、処理速度は競争優位性に直結する要素となっています。
型安全性への関心高まり 大規模システムの運用において、実行時エラーを減らすための型安全性が重要視されています。Polarsの静的型チェックは、この流れに完全に合致しています。
クラウドネイティブ設計 クラウド環境での効率的な処理を前提とした設計が求められており、Polarsのアーキテクチャはこの要求に適しています。
Pandasの対応状況と進化
Pandas 2.0以降の改善点
- PyArrowバックエンドの正式サポートによる高速化
- より堅牢な型システムの実装
- メモリ使用量の最適化
- 並列処理機能の部分的改善
Pandasの今後の戦略 Pandasプロジェクトも競争に対応するため、以下の改善を進めています:
- Arrow互換性の強化
- 遅延実行機能の実装検討
- より効率的なメモリ管理
- APIの一貫性向上
ただし、根本的な設計制約により、Polarsほどの劇的な改善は困難とされています。
まとめ:どちらを選ぶべきか
結論
PolarとPandasの選択は、プロジェクトの要件と制約によって決まります:
Pandasが適している場合
- 探索的データ分析が中心
- 既存エコシステムとの統合重視
- チームの学習コスト最小化
- 小~中規模データの処理
Polarsが適している場合
- 高性能な処理が必要
- 大規模データの定期処理
- 本番環境での安定運用
- 新規プロジェクトでのモダン技術採用
推奨アプローチ
- 現在の要件評価: データサイズ、処理頻度、パフォーマンス要求の明確化
- POC実施: 実際のデータでのベンチマーク測定
- チーム能力評価: 学習コストと開発効率のバランス検討
- 長期戦略立案: 技術スタックの将来性を考慮した選択
データ分析の世界は急速に進化しており、PolarとPandasそれぞれに適した使い道があります。重要なのは、プロジェクトの特性を正しく理解し、適切な技術選択を行うことです。
今後もこれらのライブラリは進化を続けるため、最新の動向を継続的にチェックし、必要に応じて技術選択を見直すことをお勧めします。
参照サイト・ベンチマークソース一覧
公式ソース・第一次情報
Polars公式
- Polars公式サイト - Polarsの最新情報とベンチマーク結果
- Polars PDS-H ベンチマーク - 公式のパフォーマンス測定結果
- Polarsエネルギー効率ベンチマーク - エネルギー消費量の比較研究
- GitHub: pola-rs/polars - Polarのメインリポジトリ
- GitHub: pola-rs/polars-benchmark - 公式ベンチマークコード
Pandas公式
- Pandas公式サイト - Pandas 2.0の機能とリリース情報
- GitHub: pandas-dev/pandas - Pandasのメインリポジトリ
学術・研究機関による比較研究
教育機関・データサイエンス専門サイト
- DataCamp: High Performance Data Manipulation in Python - Pandas 2.0 vs Polarsの詳細比較
- DataCamp: Benchmarking High-Performance pandas Alternatives - 複数ライブラリの包括的比較
- Towards Data Science: Pandas vs. Polars Syntax and Speed Comparison - 2025年最新の比較記事
独立研究・技術ブログ
個人研究者・エンジニアによる詳細分析
- Patrick Hoefler: Benchmarking pandas against Polars from a pandas PoV - Pandas開発者視点からの客観的評価
- Pipeline2Insights: Pandas vs. Polars Benchmarking with Real Experiments - 実データを使用した詳細ベンチマーク
- Statology: Pandas vs Polars Performance Benchmarks - UCI機械学習データセットでの比較
Medium記事・技術解説
- Medium: Comparing Pandas, Polars, and PySpark - 3つのライブラリの包括比較(2024年11月)
- Medium: Pandas 2.0 vs Polars: The Ultimate Battle - 詳細な性能比較
実践的な開発事例・GitHubリポジトリ
オープンソースプロジェクト
- GitHub: prrao87/duckdb-study - DuckDB, Polars, Pandasの実用的比較
- GitHub: jakartaresearch/polars-benchmark - インドネシア・ジャカルタ研究所による詳細ベンチマーク
- GitHub Gist: Polars Benchmark Examples - 実践的なベンチマークコード例
第三者機関による評価
FireDucks(競合ライブラリ)による中立的評価
- FireDucks Benchmarks - 複数データフレームライブラリの客観的性能比較
企業・組織による採用事例
- Ultralytics: Pandas to Polars Migration - YOLOv8開発チームによる実際の移行事例
ベンチマーク方法論・標準化
業界標準ベンチマーク
- TPC-H準拠: Transaction Processing Performance Council の業界標準テスト
- PDS-H: Polars Decision Support benchmark(TPC-H派生)
- 合成データテスト: 制御された環境でのパフォーマンス測定
- 実世界データテスト: UCI Machine Learning Repository等の実データセット使用
注意事項・免責
上記のソースはそれぞれ異なる条件・環境・データセットでテストが行われており、結果は参考値として理解することが重要です。実際のプロジェクト導入前には、自分の環境とデータでの検証を強く推奨します。
また、両ライブラリとも活発に開発が続けられているため、最新のバージョンでは性能特性が変化している可能性があります。定期的な情報更新と再評価を行うことをお勧めします。